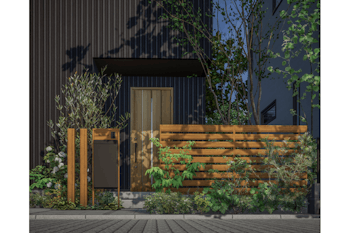太陽光発電には、自宅で電気を消費するだけではなく、余剰分を電力会社に買い取ってもらう「売電」の仕組みがあります。ただ、実際に始める前には、どれだけの金額で売電できるかは知っておきたいところです。そこでこの記事では、太陽光発電における売電の仕組みや固定価格買取制度(FIT制度)の概要、売電で得られる収入などについて解説していきます。
太陽光発電の売電の仕組み

太陽光発電は、自前の設備で生み出した電気を電力会社に売却することが可能です。それでは、太陽光発電の売電の基本的な仕組みについて見ていきましょう。
自家発電で余った電力を電力会社に売る仕組み
自宅に設置した太陽光発電システムで生み出した電力は、基本的に自家消費することになります。ただし、発電量が消費電力より多い場合、使い切れない電力(余剰電力)が発生します。余剰電力は蓄電池を持っていなければ貯めておくことはできず、使い切ることができない分の電力は、自宅から電力会社に送り、買い取ってもらうことになります。これが、太陽光発電の売電の仕組みです。
FIT制度により売電が可能
再生可能エネルギーで発電された電力は、電力会社が固定価格で買い取る制度が国によって制定されています。この制度は、「住宅用太陽光発電を含む再生可能エネルギーの固定価格買取制度」というもので、略してFIT制度とも呼ばれています。
このFIT制度は経済産業省が2012年に開始したもので、FITとは「Feed-in Tariff(フィード・イン・タリフ)」を意味しています。再生可能エネルギーでつくられた電気を、電力会社が一定の期間、固定価格で買い取る仕組みで、電力会社が買い取るための費用は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」によってまかなわれています。
FIT制度の対象となる再生可能エネルギーは、太陽光発電をはじめ、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の5種類です。一般家庭の発電設備としては、太陽光発電がほとんどの割合を占めています。
買電と売電の違い
自宅などで電力を使うためには、基本的に電力会社から電力を購入することになります。これを買電と呼びます。一方で、太陽光発電で生み出した電力を電力会社に買い取ってもらうことが売電です。基本的には日中に発電した分の余剰電力を売電し、発電できない時間帯は電力会社から買電します。
太陽光発電の売電期間と売電価格の概要
FIT制度によって固定価格で太陽光発電の余剰電力を売電することができますが、FIT制度が適用される期間は決まっています。こちらでは、FIT制度による売電期間と売電価格の概要について説明します。
売電価格が決まる仕組み
売電価格は、太陽光発電システムの設置費用や工事費用などを考慮して、毎年算出されています。経済産業省の外局である資源エネルギー庁に調達価格等算定委員会という専門委員会が設置されており、FIT制度による売電価格はこの委員会で議論され、最終的に委員長案として提出された価格を経済産業省大臣が認可して決定されるという流れです。
太陽光発電の売電期間
FIT制度の適用対象は、太陽光発電設備の規模の大きさによって、住宅用と産業用の2種類に分かれています。売電期間はそれぞれ異なり、住宅用は10年間、産業用は20年間です。つまり、住宅の場合、太陽光発電を設置してから10年間は、ずっと同じ価格で電気を買い取ってもらえます。
太陽光発電の売電価格
FIT制度がスタートした2012年度は、一般家庭向け住宅用太陽光発電の売電価格は発電容量1kWhあたり42円でした。売電価格は毎年検討され、その都度変更されていますが、太陽光発電の普及によって価格は年々下落を続けています。2022年度は1kWhあたり17円、そして2023年度は16円に設定されました。
住宅用と産業用の売電制度の違い

一般の住宅に設置される太陽光発電と、一度に多くの電力を生み出せる産業用の太陽光発電では、FIT制度の仕組みが異なります。こちらでは、それら2つの違いについて見ていきたいと思います。
発電容量の大きさ
FIT制度は、太陽光発電システムの出力の大きさによって適用条件が変わります。出力10kWを境に住宅用と産業用(事業用)に分かれており、10kW未満が住宅用で、10kW以上が産業用という扱いです。
住宅用太陽光発電のFIT制度
FIT制度では、10kW未満が住宅用太陽光発電とされています。売電できる期間は10年間で、買取金額は前述の通り2022年度が17円で、2023年度は16円です。金額は固定なので、たとえば2022年度にFIT制度を開始した場合は、17円での売電が10年間続いていくという仕組みです。
実際に住宅用として設置される太陽光発電システムは3~5kWが主流ですので、一般的な製品を選ぶことで住宅用のFIT制度が適用されます。自宅の屋根の面積が大きく、かつ設備投資のための予算に余裕があるなら、10kW近い容量にして多く発電することも可能です。
産業用太陽光発電のFIT制度
太陽光発電システムの出力が10kW以上の場合、産業用太陽光発電に当てはまります。なお、厳密には産業用でも2種類あり、10kW以上50kW未満と、50kW以上に分かれます。売電価格は、10kW以上50kW未満が10円で、50kW以上が9.5円です。買取期間は、産業用の場合はいずれも20年間と、住宅用よりも長く設定されています。
FIT終了後の売電価格
前述の通り、FIT制度の期間は住宅用が10年間、産業用が20年間と定められています。では、制度が適用される期間が終了してしまったら、その後はどうなるのでしょうか。売電ができなくなるのかどうか、価格はどうなるのかという点については、気になるところです。こちらでは、FIT終了後の売電の仕組みについて解説していきます。
11年目または21年目以降も売電は可能
FIT制度の期間は、住宅用で10年間、産業用で20年間です。たとえば、住宅用では11年目以降は、もう適用されません。FIT制度の期間が終了した状態は「卒FIT」と呼ばれ、補助金の充当が無くなります。しかし、売電自体は続けることが可能です。ただ、売電価格は大幅に下がってしまうので、FIT期間と同様の収入を得ることは難しくなります。
卒FITを迎えるタイミングは、各家庭のFIT制度の開始時期によってそれぞれ異なります。近所の人や知人が卒FITを迎えていないからといって自分の家もまだというわけではありません。心配であれば、自分の家がいつFIT制度を始めたのか確認しておきましょう。
住宅用の卒FIT後
FIT制度が施行されたことによって、太陽光発電は急速に普及しました。その流れから、太陽光パネルを設置する費用は年々低下を続けています。同様に売電価格も下がっている状況です。また、FIT制度では補助金が充当されていましたが、卒FIT後には適用されません。
そうした背景から、電力会社や地域によって価格は異なるものの、基本的に売電価格は10円前後とFIT期間中よりも下がってしまいます。ただ、買い取ってくれる価格が高い電力会社や事業者と契約すれば、卒FIT後の収入の減少幅も少なくすることが可能です。
産業用の卒FIT後
産業用太陽光発電の場合、FIT制度は20年間と長期にわたります。20年もあれば、太陽光発電システムの設置にかかった費用は、回収している可能性が高いでしょう。FIT制度がスタートしたのは2012年度ということで、産業用太陽光発電で卒FITが発生するのは2032年度からです。電力会社などからの具体的な発表はまだないが、住宅用のように卒FIT向けの買取プランが出るかもしれません。
卒FIT後の選択肢

卒FITを迎えた場合、太陽光発電システムを引き続き有効活用することはできるのでしょうか。卒FIT後に取りうる選択肢を挙げてみましたので、参考にしてください。
売電する電力会社を変える
卒FIT後は、余剰電力を買い取るサービスを提供している電力会社と自由に契約することが可能です。その中から、条件の良い会社を探して売電すれば、FIT期間中からの収入減を少なくすることができます。たとえば、大手電力会社の場合、東京電力は8.5円、関西電力は8円、中部電力は7~12円と差が見られます。一方で、いわゆる「新電力会社」である伊藤忠エネクスが提供する「太陽光電力買取サービス」の単価は、関東エリアで最高14.5円と電力会社よりも高めです。このように差は大きいので、できるだけ高い収入を得たいのであれば、電力会社や事業者の買取価格をしっかり調べてから契約しましょう。
自家消費する
余剰電力を、積極的に自宅で消費する方法です。電気の自給自足が進めば、電力会社から購入する電気が減少。毎月の電気代を抑えることができるようになります。単に自家消費を増やすだけではなく、EV(電気自動車)を蓄電池の代わりに使ったり、エコキュートや定置型蓄電池を導入したりすることで、電力会社からの購入量をゼロに近づけることも可能です。このように、収入を得るかわりに電気代という支出を減らすというアプローチもあります。
まとめ
FIT制度は、太陽光発電を売電する仕組みとして定着しています。ただ、この制度によって一定の売電収入を得ている家庭も、期限を迎えたら卒FITをしなければなりません。卒FIT後は、どのような状況が想定されるのか。売電収入というメリットだけではなく、FIT制度のその先も見据えて余剰電力の最適な使い方を模索しましょう。
※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。