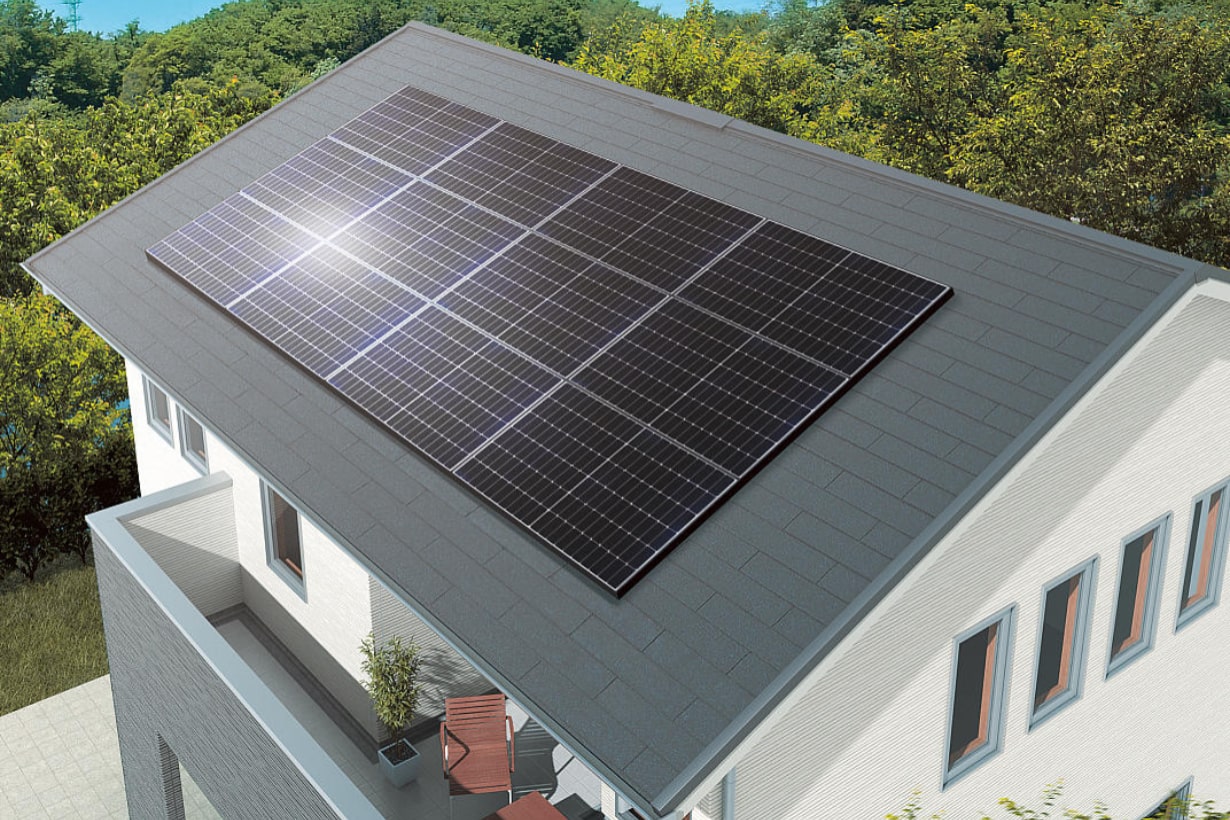災害時に備えて、蓄電池を導入する家庭が増えています。しかし、本当に蓄電池の必要性があるのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、蓄電池の必要性、導入するメリット・デメリット、蓄電池の選び方、補助金について紹介します。
蓄電池の必要性とは?

蓄電池は電気を蓄えておけるため、電気を使う・売る・保存するということが可能です。電気代を節約したり、停電時に使用したりすることが、蓄電池の主な役割になります。
太陽光発電を導入している場合は、日中は太陽の光を利用して発電し、余分な電気は売ることが可能ですが、ためておくことはできません。夜間は、電力会社から電気を購入する必要があります。蓄電池があれば、併用して日中発電した電気を夜間に使用することが可能です。
また、自家発電した電気は、発電機導入から10年を過ぎると売電価格が下がります。蓄電池を導入して好きなタイミングで電気が使用できれば、発電した電気を有効活用できます。
蓄電池の需要は年々伸びている
蓄電池を導入する家庭は、年々増加しています。日本電機工業会の統計によると、2021年度時点で蓄電池の累計出荷台数は約62万台です。2011年から統計を取り始めて以降、出荷台数は右肩上がりで、2021年度は1年間で約13万台もの蓄電池を出荷しています。
|
2011年度 |
2012年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
| 出荷台数 |
1,939 |
11,449 |
16,559 |
23,716 |
37,560 |
34,562 |
49,481 |
73,594 |
115,000 |
126,925 |
133,759 |
※参照:一般社団法人 日本電機工業会「JEMA 蓄電システム自主統計」
災害に対する意識の変化や卒FITした家庭が増えたことが、需要が伸びている一因であると考えられます。蓄電池のニーズは今後も伸びていくでしょう。
蓄電池を導入するメリット

蓄電池には、以下の4つのメリットがあります。
- 停電しても電気が使える
- 電気代を節約できる
- ピークシフトができる
- 卒FIT後でも電気を有効活用できる
特に太陽光発電を導入している家庭では、蓄電池を導入するメリットが非常に大きくなります。蓄電池の導入はどのような点で得するのか確認し、導入を検討してみましょう。
停電しても電気が使える
蓄電池の大きなメリットは、災害時や非常時に停電しても、蓄えた電気を使えることです。電気が使えないと、以下のようなさまざまな問題が発生します。
- 冷蔵庫の食品が使えなくなる
- 夜は部屋が真っ暗になり不便
- 冷暖房器具が使用できず、体調が悪化する
- テレビなどが使用できず、情報収集できない
- スマホの充電ができなくなる
災害などで停電になった場合は、電気がいつ復旧するのか分かりません。蓄電池があれば、上記のような問題を防いでトラブルを回避できます。
また、健康管理のために医療機器を利用している方がいる家庭では、電気の使用は死活問題です。蓄電池を導入して非常時にも電気が使えるようにしておけば、いざというときに安心でしょう。
電気代を節約できる
蓄電池を導入すれば、電気代を節約できるのも大きなポイントです。電気代が安い夜間に購入して蓄えておき、日中に使用すれば電位代を節約できます。オール電化の住宅の場合、特に節電効果を実感しやすいでしょう。
太陽光発電を導入している家庭ならば、日中に発電した電気を蓄電池へためておき、夜間に使用できます。電気を自給自足できるため、ほとんど電気代をかけずに済むでしょう。
ピークシフトができる
夏や冬は、エアコンなどの冷暖房器具を多くの家庭で使用します。電気を使う家庭が多いと、電気の需要が高まって電気代が高騰します。電気の購入を、電力の消費が激しい時間帯からずらすのがピークシフトです。
蓄電池があれば、電力消費が多い時間は蓄電池からの供給に切り替えることができます。電気代が高騰している時間に電気を購入する必要がなくなるため、電気代を抑えることが可能です。夏・冬の電気代が特に高い場合は、節約効果を期待できるでしょう。
卒FIT後でも電気を有効活用できる
太陽光発電を導入してから10年が過ぎると、FITで定められた価格よりも安い価格でしか売電できなくなります。売電価格は電力会社によって異なりますが、電気を購入するときの価格よりも低く設定されることがほとんどです。
卒FIT後に蓄電池を導入することで、発電した電気を蓄えて使用できるため、電力会社から電気を購入する機会が減ります。売電するよりも経済的なメリットが高まり、発電した電気を有効活用できるでしょう。
蓄電池を導入するデメリット
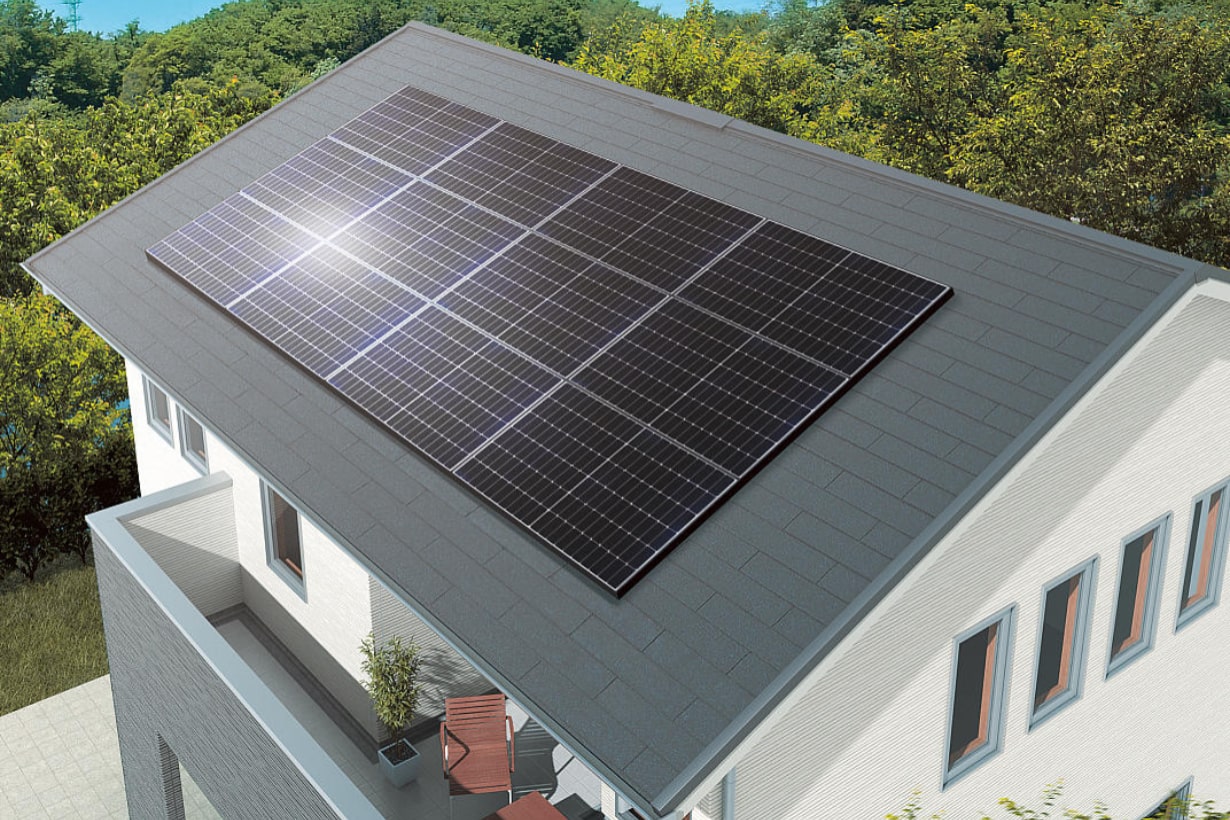
蓄電池には、以下の4つのデメリットがあります。
- 初期費用が高額
- 寿命が10~20年
- 設置スペースを確保する必要がある
- 元が取れない可能性がある
電気代の節約のみを目的にしている場合は、使い方次第では損をすることもあるため注意しましょう。
初期費用が高額
蓄電池の導入費用は100~300万円と高額です。価格は電力を蓄えられる量や機能などで変動します。安価なものもありますが、機能や保証に不安な面もあるため、避けた方がよいでしょう。家庭で消費する電力量などを計算し、無駄なく活用できる蓄電池を選ぶのがおすすめです。
寿命が10~20年
蓄電池で充電・放電を続けると、劣化が進んで蓄えられる電気量が徐々に減少します。多くの蓄電池ではリチウムイオン電池を採用しており、サイクルは平均6,000回ほどです。
蓄電池の寿命は10~20年と言われており、時期が来たら買い替える必要があります。蓄電池の種類によって電池のサイクルも異なるため、より長い寿命のものを選びたい場合は、サイクルを考慮するとよいでしょう。
設置スペースを確保する必要がある
蓄電池は室外機と同じくらいの大きさがあり、設置スペースを確保する必要があります。最近は小型化されたモデルもありますが、容量が大きいほど蓄電池のサイズも大きくなることがほとんどです。
また、何かあったときにメンテナンスできるように、設置する場所には修理できる空間を確保する必要もあります。蓄電池を導入する際は、設置できる場所があるかどうか確認しておきましょう。
元が取れない可能性がある
蓄電池の導入には100万円以上かかるため、寿命を迎える10~20年で初期費用を回収できない可能性があります。例えば、100万円の蓄電池を10年使用すると、1年間でかかる費用は10万円です。1年間でかかる電気代が10万円未満の場合は、初期費用を回収できません。節約だけを目的にして蓄電池の導入を考えている場合は注意が必要です。
一方で、太陽光発電を導入している場合や、災害に備えるために蓄電池を導入する場合は、節電以外にも導入する意義があるため、損をするとは限りません。蓄電池をどのような目的で使用したいのか、よく検討するとよいでしょう。
蓄電池の選び方

蓄電池はさまざまなメーカーから販売されており、何を基準に選んだらよいのか迷う方もいるでしょう。自宅に合った蓄電池を選ぶには、蓄電量・蓄電タイプ・コストパフォーマンス・負荷型の4つに注目するのがポイントです。
ここでは、蓄電池の選び方についてそれぞれ詳しく解説します。
蓄電できる量で選ぶ
適した蓄電量は、家族の人数や使用方法によって異なります。普段の電力消費量はどれくらいか、停電時にどれくらい供給されればよいかなどを考慮して決めるようにしましょう。太陽光発電を導入している場合は、発電量と蓄電量が見合っているか確認する必要があります。
タイプで選ぶ
蓄電池には、独立型・連係型・EV対応型の3タイプがあります。ここでは、それぞれの特徴を紹介します。
独立型
電力会社から購入した電力を蓄電するのが独立型です。蓄電した電力は、使いたいタイミングでいつでも使用できます。電気代が安い深夜に電力を蓄え、昼間に電力を購入しないようにすることで電気代を節約できます。
独立型には、ブレーカーにつなげるタイプや、コンセントに差し込むタイプなどがあるため、用途に合わせて選びましょう。
連係型
電力会社が供給する電力と、太陽光で発電した電力を蓄えておけるのが連係型です。長期間の停電にも対応できるため、非常時の備えに向いています。
連係型には、パワーコンディショナが2台必要な単機能型と、1台で済むハイブリッド型があります。
EV対応型
EVとは電気自動車のことです。電気自動車から充電・放電し、蓄電池に電気を蓄えます。電力会社から購入した電力と、太陽光発電の電力の2つを蓄電できるタイプもあります。
独立型・連係型よりも容量が大きいものが多く、余裕をもって運用できるのがメリットです。
コストパフォーマンスで選ぶ
蓄電池は使い続けると蓄電量が減るため、いずれは買い替える必要があります。充放電回数や逓減率を考慮せずに価格だけで購入を決めてしまうと、コストパフォーマンスが悪く損をすることもあります。
例えば、10年間使用した際に、蓄電量が何%まで減るのかは蓄電池によって異なります。コストパフォーマンスを重視する場合は、長期間利用しても蓄電量があまり減少しないものを選ぶとよいでしょう。
特定負荷型か全負荷型かで選ぶ
蓄電池には、一部分のみに電気を使用できる特定負荷型と、家全体の電気をまかなえる全負荷型の2種類があります。
特定負荷型は、全負荷型よりも長い時間電気を使用できます。ただし、停電時には特定の部屋や電化製品のみしか使用できないため注意が必要です。
全負荷型は、停電時でも普段と同じように電気を使えるのがメリットです。ただし、使用する電気量が多いため、長時間の使用はできません。なるべく長く使用するには、電気の使い方を工夫する必要があるでしょう。
蓄電池の導入に補助金は使える?
蓄電池の導入費用は高いため、補助金を活用したいと考える方は多いでしょう。蓄電池の補助金は、国と地方自治体がそれぞれ募集をしています。
なお、補助金は国と地方自治体どちらか一方だけでなく、両方受給することも可能です。受給条件をよく確認し、補助金の申請をしましょう。
国の補助金制度
国の補助金制度には、DER補助金やストレージパリティ補助金などがあります。要件を満たしていれば、どの地域に住んでいても申請可能です。
ただし、補助金を受給できる条件が細かいため、自分が条件に当てはまるかどうか、しっかり確認する必要があります。補助金制度の詳細については、経済産業省や環境省の補助金に関するホームページで確認可能です。
地方自治体の補助金制度
県や市町村といった地方自治体も、それぞれ独自に補助金を出しています。蓄電池に関する補助金が必ず出ているとは限りませんが、お住まいの自治体に補助金があるかどうか、ホームページを確認してみましょう。
補助金の申請は先着順であり、人気の場合は早期に受付が終了することもあります。補助金が出るのは4月であるため、早めに申請するのがおすすめです。
なお、補助金の申請は業者が代行してくれる場合もあります。どのような補助金があるのかも含め、一度相談してみるとよいでしょう。
まとめ
蓄電池の導入には高額な初期費用がかかりますが、災害などで停電したときに非常に役立ちます。太陽光発電を導入している家庭ならば、電気代を大幅に節約することも可能です。蓄電池にはさまざまな種類があるため、特徴をよく確認してから選ぶようにしましょう。補助金を活用すれば、自己負担額を減らすことができます。
※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。