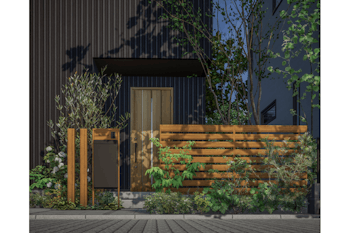リフォーム詐欺の件数は増加傾向にあり、騙されてしまう人が後を絶ちません。騙されないようにするには、詐欺の手口を知って対策を立てることが大切です。この記事では、リフォーム詐欺の件数、よくある手口、詐欺業者の特徴、騙されたときの対処法について紹介します。
リフォーム詐欺の件数

国民生活センターに寄せられる相談件数を見ると、訪問販売・点検商法ともに相談件数が毎年増えています。今後も増加することが予想されるため、注意が必要です。
|
2019 |
2020 |
2021 |
| 訪問販売の相談件数 |
8,007件 |
8,784件 |
9,734件 |
| 点検商法の相談件数 |
5,760件 |
7,023件 |
7,421件 |
※参照:国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」
詐欺件数が増加しているのは、請負代金が500万円未満のリフォームの場合は、建設業許可を受けずに営業できることが理由だと考えられます。軽微なリフォームであれば資格が不要であるため、技術やノウハウのない業者でも仕事の受注が可能です。そのため、手抜き工事をしたり、工事をせずに逃げたりするリフォーム詐欺が横行しています。
よくあるリフォーム詐欺の手口

リフォーム詐欺の手口は、ある程度パターンが決まっています。以下で紹介する手口に当てはまる場合は、詐欺である可能性が高いため警戒するようにしましょう。
不安を煽って契約を迫る
よくある詐欺の手口は、「柱が傷んでいる」「このまま放置すると家が傾く」など、大げさな表現で不安を煽って契約を迫るケースです。「対応しないとまずいのかも」と業者の言うことを信じてしまう人も多いですが、実際は早急な対応が必要ではないケースがほとんどです。
優良な業者であれば、わざわざ不安を煽るような言葉は使いません。何を言われても冷静さを失わず、相手の言うことが本当なのか疑問を持つようにしましょう。
無意味な耐震工事をして高額請求する
自宅に訪問し、「耐震基準を満たしていない」などと嘘をついて、意味のない耐震工事を行う詐欺があります。すぐに見積もりを出してその場で契約を迫り、後から高額な工事費用を請求してくるケースが大半です。
しかし、耐震診断は外観を見ただけで判断できるものではなく、見積書の作成にも時間がかかります。すぐに契約を迫るのは悪徳業者の可能性が高いため、少しでも怪しいと感じたら契約しないようにしましょう。
補助金・火災保険で工事がタダになると嘘をつく
「補助金や火災保険を利用して無料でリフォームできる」と言って契約を迫る手口も、よくある詐欺手法です。実際には補助金や火災保険が下りず、全額自腹で支払わなければならないケースがあります。実際に補助金や火災保険を利用できるケースもありますが、必ず利用できるとは限りません。
補助金を受け取るには、工事着工前に申請し、コンサルタントによる調査・診断が必要です。補助金の支給件数には限りがあり、人気の補助金は応募者が殺到してすぐに受付を終了する場合があります。また、補助金支給の条件に当てはまらず、申請が通らない場合もあります。
火災保険の場合は、台風などの自然災害による劣化など、条件を満たさないと保険金が下りません。経年による劣化の場合は利用できないため注意しましょう。
仮に補助金や火災保険が利用できても、支給額には上限が設けられているケースがほとんどです。リフォーム費用の全額を補助金などでまかなえるとは限らないため、「無料で」などと耳あたりの良いことを言ってくる業者には注意しましょう。
自作自演で不具合を指摘する
わざと住宅の一部を壊し、不具合があると指摘してくる悪質な業者もいます。主な手口は、水道管を切って漏水させたり、配線を切って漏電させたりするなどの方法です。
また、シロアリの点検商法では、実際にはシロアリがいないにもかかわらず、持参したシロアリを見せて「シロアリがいるため危険」と嘘をつくケースもあります。
もともと不具合があったのか、業者が自作自演したのかを判断するのは難しいですが、業者が来たタイミングで都合良く問題が見つかった場合は怪しんだ方が良いでしょう。
代金支払い後に業者と連絡が取れなくなる
訪問販売に訪れた業者とその場で契約して代金を支払ったものの、その後業者と連絡がつかなくなったり、工事が途中で中止になったりするケースがあります。連絡先に電話しても、つながらないことがほとんどです。
なお、契約書に工事予定日が記載されているのに工事が始まらない場合は、代金を支払った後でも契約を解除でき、工事代金の返還を要求できます。訪問販売に訪れた業者とは基本的にその場で契約しない方が良いですが、リフォーム業者と契約を結ぶ際は、必ず契約書を交わすようにしましょう。
リフォーム詐欺業者の特徴

ここからは、リフォーム詐欺業者の特徴について紹介します。以下で紹介する特徴に当てはまる業者は、後から高額請求したり、手抜き工事をしたりする可能性が高いため注意しましょう。
無料点検から契約に持ち込もうとする
アポなしで訪問し、無料点検を口実に自宅を見て回る点検商法は、リフォーム詐欺業者の常とう手段です。点検後、欠陥を指摘して不安を煽り、契約を取り付けようとしてきます。
無料なら見てもらおうと考える人も多いですが、受け入れてしまうと悪徳業者の思うつぼです。点検後に契約を迫られたとき、心理的には「無料で点検してくれたから」と業者の提案を承諾しやすくなってしまいます。
被害にあわないために、業者が訪問してきてもドアは開けず、無料点検はきっぱりと断ることが大切です。
大幅な値下げを提案してくる
契約を迫る途中で大幅な値下げを提案してくる場合は、詐欺の可能性が高いでしょう。このようなケースは最初から値引きを考慮し、もとの値段を高く設定している場合があります。また、他のリフォーム会社と比べて費用が安い場合は、人件費や材料費を削っている可能性が高いです。安い費用では品質が保てないため、手抜き工事になります。
優良業者ならば、品質確保のために大幅な値下げをすることはありません。「安いならやってもらおう」と考えず、なぜ安くなるのか理由を疑うようにしましょう。
相談から着工までの期間が短すぎる
悪徳業者は訪問したその日に見積もり・契約を完了させ、工事を始めようとします。手続きを素早く進めることで、冷静になって考える時間を与えないようにしているためです。
優良なリフォーム会社であればしっかり手順を踏んで契約するため、リフォームの相談から着工まで半月ほどはかかります。たった数日で手続きを終える業者は詐欺の可能性が高いため注意しましょう。
リフォーム詐欺を相談できる公的機関

リフォーム詐欺にあったとき、どうすれば良いのか相談したい場面もあるでしょう。ここでは、リフォーム詐欺について相談できる公的機関を3つ紹介します。技術的な相談や法律の相談など、機関によって対応してもらえる範囲が異なるため、各機関の特徴を押さえておきましょう。
住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、法律に基づいて国土交通大臣から指定を受けた公的な相談窓口です。相談は原則無料で、対応してくれる相談員は建築士であるため、「リフォーム費用は妥当か」「業者の説明は正しいか」などの技術的な相談ができます。
また、弁護士にも相談可能で、詐欺の被害にあわないための予防的な相談もできます。ただし、「クーリング・オフは可能か」などの法的な相談は専門家相談となり、無料で相談できる時間は1時間に限られているため注意しましょう。
リフォームに関する電話相談のほか、郵送による契約前の見積りチェックも受け付けています。専門家の意見を詳しく聞きたい場合は、住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談すると良いでしょう。
日本建築家協会(JIA)
日本建築家協会(JIA)は、建築家団体による公益社団法人です。リフォームの詐欺やトラブルなど、建築物に関する消費者からの相談を2回まで無料で受け付けています。「業者にすぐに対応しないとまずいと言われたが、本当にそうか確認したい」など、技術的な相談が可能です。相談には弁護士が同席することも可能ですが、無料で対応してもらえるのは1回のみとなります。
日本建築家協会による相談は、電話相談は受け付けておらず、対面のみの対応のため注意しましょう。なお、相談した結果、具体的な調査が必要になった場合は別途費用が必要となります。
国民生活センター
国民生活センターは、購入した商品やサービスなど、消費者トラブルに関する相談を受け付けている機関です。過去の被害報告や業者へのクレームなどを確認できるほか、無料相談も受け付けています。
「トラブルは解決したいが、裁判は起こしたくない」「自分だけの力では解決できそうにない」などの場合は、仲介・仲裁を行うADR(裁判外紛争解決手続)を紹介してもらうことができます。また、消費者団体訴訟制度(団体訴権)を紹介してもらい、消費者に代わって不当な行為をやめさせるよう裁判で請求することも可能です。
リフォーム詐欺にはクーリング・オフ制度が適用できる
万が一リフォーム詐欺の被害にあっても、訪問販売でのリフォーム工事契約が契約日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度で解約できます。クーリング・オフすれば、すでに工事が終了していても代金を支払う必要はありません。工事した部分をもとに戻してほしい場合は、無償で工事を請求することができます。
ただし、クーリング・オフ制度が適用できないケースもあります。自分から業者の営業所を訪れた場合や、自分で自宅に業者を招いて契約した場合などです。クーリング・オフ制度の適用は、訪問販売や電話勧誘などで契約したものに限られるため注意しましょう。
まとめ
リフォーム詐欺には、不安を煽って契約を迫ったり、耳あたりの良いことを言って契約を承諾させようとしたりなど、さまざまな手口があります。アポなしで訪問してきた業者は警戒し、相手をしないことが重要です。リフォーム詐欺に騙されないように、手口や悪徳業者の特徴を知って対策を立てるようにしましょう。
※当ページのコンテンツや情報において、カインズリフォームでは、取り扱いが異なる場合がございます。